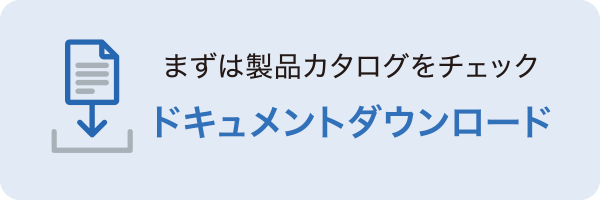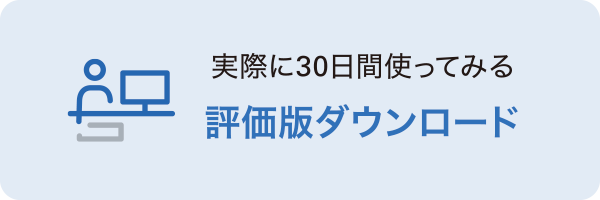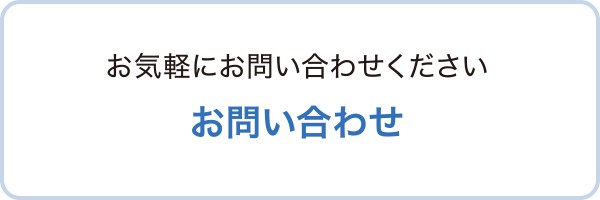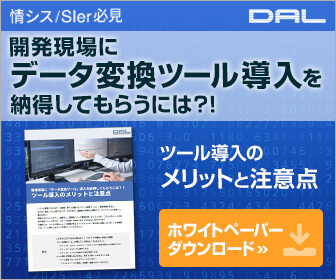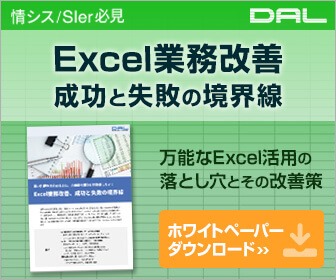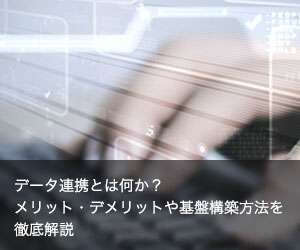データ活用・データ連携のお役立ちコラム
EAIとは?ETLとの違いやツール導入のメリットも解説!
最終更新日:2023/08/31
ICTが高度に進歩した今日、企業はERP(Enterprise Resource Planning)やEDI(Electronic Data Interchange)、CRM(Customer Relationship Management)といったさまざまなシステムを導入しています。一方で、多くの企業はそうしたシステムから必要な情報を迅速に取得できる状況にはありません。業務・部門ごとに開発したシステムがほとんどであり、各システム上にデータが分散したままとなっているからです。このような課題を解決するために、EAI(Enterprise Application Integration:企業アプリケーション統合)ツールを導入する企業が多くなっています。そこで、このコラムではEAIとはそもそもどのようなものなのかといったところから、EAIツールの機能や導入メリットを解説します。
INDEX
- EAIとは?
- EAIとEDIの違いとは?
- EAIツールの基本機能とは?
- EAIツール導入のメリットは?
- EAIツールとETL/ESBツール、どこが違うの?
- EAIツール選定のポイントは?
- EAIの活用事例
- まとめ
EAIとは?
EAI(Enterprise Application Integration)とは、企業内で使用される複数の異なるシステムを連携させ、各々のデータやプロセスを効率的に統合する仕組みおよびそのシステムです。
これまで、システムやデータの連携を実現するには、インターフェースやプログラムを個別に開発する必要がありました。この手法だと、各システムに改修やバージョンアップが必要になると、そのつど改修しなければなりません。そのため、このEAIという工程には多大な工数とコストが発生していました。しかし、データやプロセスの統合に必要な機能を搭載しているEAIツールの登場によって、こうした状況が変わりつつあります。
EAIとEDIの違いとは?
システムやデータの連携というと、EDIという概念も存在します。EAIとEDIの違いとは何でしょうか。
EDIは、企業間でデータをやり取りする際に使われます。それも、主にB to Bの受発注取引に関する情報を対象にしており、この工程を効率化することが目的です。
それに対してEAIは、社内システム間のシステムやデータの連携を対象にしています。つまり、EDIは社外との連携、EAIは社内での連携というわけです。ただ最近は、EDIとEAI、双方のニーズを同一システムで満たすものも出現しており、特に守備範囲を区別する必要がなくなってきました。
EAIツールの基本機能とは?
EAIツールは、一般的に異なるシステムを連携させるミドルウェアとして提供されています。その主な機能は、次の通りです。
アダプタ機能
連携したいシステム群の中心にハブとして存在して、各システム間とのデータ授受を実現する機能です。従来のように、各システム間のインターフェースやプログラムを個別に開発する必要がなくなります。
変換機能
各システムから受け取ったデータを変換する機能です。この機能により、異なる形式やプロトコルのデータ同士を連携することができます。
フロープロセッサ機能
受け取ったデータの内容に合わせて、配信先と配信順序を自動的に決定する機能です。
プロセス制御機能
上記3つの機能を組み合わせて、目的とするデータ処理を実行するための制御を行う機能です。多くのツールでは、プログラムをコーディングすることなく、GUIを使って簡単にプロセスを定義付けすることができます。

EAIツール導入のメリットは?
システム間データ連携の高速化
インターフェースやプログラムを個別に開発した場合、その性能はプログラミングの良し悪しに左右されます。また、その方式が属人化されるリスクもあります。しかし、ツールであれば、この工程があらかじめ標準化・最適化されているため、どの組織もデータ連携の高速処理を享受できます。
運用開始までの工数の大幅な削減
前述の通り、EAIツールを活用すればインターフェースやプログラムを個別に開発する必要がなくなります。また、EAIツールの多くには直感的に操作できるGUIが搭載されています。そのため、この領域に精通したエンジニアがいなくてもこの工程が実現でき、データ連携に必要な作業自体も効率化可能であるため、運用開始までの工数を大幅に削減できます。
システム改修やバージョンアップへの迅速な対応
連携するシステムに改修やバージョンアップが発生した場合にも、ユーザ自身がプログラムをコーディングし直す必要がなくなります。GUIを使った直感的な操作で改修できるため、迅速に対応することができます。
ヒューマンエラーの防止
データ入力やプログラム開発において、手作業が多くなればなるほどヒューマンエラーの発生する可能性は高まります。EAIツールを導入すれば、システムの統合に必要な作業の多くを自動化することができます。そのため、ヒューマンエラーによるデータの誤変換・喪失などを防ぐことが可能です。
EAIツールとETL/ESBツール、どこが違うの?
データやシステムの連携を実現できるITとしては、ETLツールやESBツールも存在します。では、この2つのツールとEAIツールとの間にはどのような違いがあるのでしょうか?
ETLツールとEAIツールとの違いとは?
ETLは、Extract・Transform・Loadの頭文字を取ったIT用語です。このツールは、データの抽出・変換・書き出しを行うことによって、データを集約・統合することを目的としています。その用途も、高度なデータ分析やデータマイニングが主であり、基本的にバッチ処理で実行します。
一方、EAIツールは、データを単一のデータウェアハウスやデータマートに集約することを目的とはしていません。CRMやERPなどを使った業務システムやメインフレームシステム、Webシステムといったシステム間の違いを吸収しながら、複数アプリケーションを通じてデータをやり取りすることが主眼です。
このように、ETLツールはバッチ処理を基本としたデータ集約を実現するツールで、EAIツールはアプリケーション統合によりリアルタイム処理を実現するツールという点に違いがあります。
ESBツールとEAIツールとの違いとは?
ESBは、Enterprise Service Bus(エンタープライズ・サービス・バス)の頭文字を取ったIT用語です。バスとは、コンピュータ内外の各回路がデータを交換するために使用する共通の経路を意味します。
ESBは、SOA(Service Oriented Architecture:サービス指向アーキテクチャ)という概念に基づいたアプリケーション統合を実現する上で使用されます。具体的に、各システムのビジネスプロセスをサービスという単位に細分化したうえで、それらを組み合わせることで新たなアプリケーションを構築します。ここで、そのような分散したサービスどうしを組み合わせる役割を担うのがESBツールです。一方、EAIで扱うビジネスプロセスの粒度はもっと大きく、EAIツールはハブ&スポーク型の集中処理を採用しているという点でESBツールとは異なります。
EAIツール選定のポイントは?
EAIツールの選定においては、次の4つのポイントから比較検討しましょう。
システムのデータ連携と処理を可視化できる仕組みがあること
運用開始までの作業や運用開始後のシステム改修やバージョンアップへの対応を迅速に進めるには、データ連携とデータ処理を可視化できる仕組みが必要です。
高いセキュリティ性を有すること
セキュリティ標準に対応したデータの暗号化や、ファイル転送時に無駄なファイルコピーを残さない仕組みが求められます。
24時間x365日稼働する高可用性と耐障害性を兼ね備えていること
EAIツールは、ピークの異なる、多岐にわたったシステムのデータを扱います。そのため、24時間365日稼働できる高可用性と、ハードウェア障害とソフトウェア障害に対する耐障害性を兼ね備えていることも重要な選定条件となります。
クラウドとオンプレミス間の連携ができること
組織には、まだまだオンプレミスで動かす必要のあるシステムが多いものです。クラウド型のEAIツールを利用する場合は、これらとの連携に問題はないかをチェックすることが必要です。
EAIの活用事例
活用例
あるメーカーではアフターサービス体制の刷新を機にシステム間連携を見直し、そのインターフェース環境をEAIで統一。拠点を超えた情報共有や業務自動化を実現させました。一方、あるITベンダーは、サブスクリプションモデルに移行する中で、ソフトウェアとサービスの課金方法に関して新しい情報統合基盤を模索。EAIを用いることでパフォーマンスや拡張性を向上するとともに、コスト削減も達成しました。さらに、ある出版社は刷新した基幹業務システムと物流システムとの連携にEAIを採用。これが受注業務や在庫管理の時間短縮に貢献しています。
まとめ
ここまで、EAIの概要、そしてEAIツールの役割や機能について見てきました。EAIは大きな業務改革につながり、DXを促進します。これから導入を検討するという場合は、その将来性も見据えながら、自社に合ったEAIツールをお選びください。
この記事の執筆者
-
明石市役所
メインフレームからオープン環境への国民健康保険システム移行
PC1台で数千万件のデータ変換を13時間で可能としたRACCOON -
楽天カード株式会社
数TBに上るメインフレームデータのオープン移行
16時間でデータ変換を完了したRACCOON -
小泉産業株式会社
EDIシステムの刷新をきっかけに
ACMS Apex + RACCOONで、グループ全体のデータ連携基盤を実現 -
株式会社カナデンブレイン
基幹システム製品のクラウド化で求められたデータ移行工程の見直し
RACCOONで精査が必要なデータを簡単かつ高品質に移す体制を確立 -
スズデン株式会社
めざしたのは4通販サイトへのデータ提供の自動化
RACCOON導入で情報の精度・スピードが一気に向上 -
ネスレ日本株式会社
基幹EDIインフラをAS/400からAWSへ
ACMS Apex、RACCOONが短期開発に貢献